冨樫 道廣 (会員)
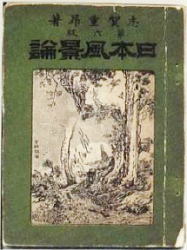 |
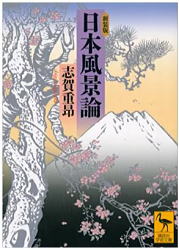 |
| 1.第6版 政教社 | 2.新装版 講談社2014 |
「諸論」の1ページを紹介してみよう。
「第一江山洵美(ジュンビ)はるかわが郷」「大槻磐渓(オオツキバンケイ)と身世(シンセイ)たれか我が郷の洵美をいわざるもの…(以下略)」
この様な文調で続くもので、筆者は10ページでギブアップしてしまったのが本音である。ところが何年か経って、たまたま岩波現代文庫の中に「精読シリーズ」という企画があり、その中に志賀の「日本風景論」が、2番目に掲げた大室幹雄の著(2003年)となって、書店の本棚に並んでいたのである。(右下写真)幸運とばかり買い求め、ワクワクしながら読み出したが、これまた単なる本書「日本風景論」の本文解説に終わるものではなかった。それに倍する紙幅をとって、志賀の意図するところから、その時代の社会的、時代的背景などと同時に、その当時の人々が様々なレベルに応じてどの様な反応があったかなどを、著者の識力、迫力を持って、当時の新聞諸評だけでなく、学会誌や学内誌までその調査は浸透していく。その著者の努力には敬服せざるを得ない。
そこで本稿では、2回の紙面を頂戴して「前篇」として、「精読」の項から「日本風景論」の時代的社会的背景と、志賀自身の意図などを考察して、次回の後篇として具体的に「日本風景論」を精読してみたいと思っているところです。
では早速、前篇をスタートすることにしよう。
大室幹雄著の「精読」に沿うならば、志賀の紹介は「日本ライン」から始まる。というのは、著者が教室で学生に「日本ライン」を知っているかと聞いても皆誰も知らないと言う。更に研究室に連れて行って大きな日本語辞典「大辞泉」(小学館1995)を引いてみたところ、「木曽川中流の渓谷の称。(中略)長さ13キロ、ドイツのライン川に似ているというので、大正時代に地理学者志賀重昂(しがしげたか)が命名。舟による川下りの観光地。」と記されている。又地図をと探せば国土地理院発行の5万分の1の地形図を二面合せると南北のほぼ中央に可児市と美濃加茂の境を蛇行している大きな川が画かれて「日本ライン」と表示されている。今や若い人達にはなじみがなくとも「日本ライン」は健在なのであると、著者の確認である。しかしこれで志賀の紹介が済んだわけでもない。
志賀の「日本風景論」の再版過程を調べてみると、その重版の速度は異状とも言われる程で、初版が出された明治27年(1894)の翌年、明治28年3月には3版まで、更には明治35年(1902)4月までには14版までに上る。時あたかも、近代日本が迎えた初めての対外戦争の真中であった。志賀は、「国粋保存主義」の主唱者として政教社を設立、「日本人」を創刊したりして対外硬論を展開したのであった。しかしその反面も垣間見られるところもある。政治思想家の萩原隆・名古屋学院大教授によれば、「志賀が国粋主義者として風景に着目したことに評価しながらも、引き合いに出される風景は高山や火山、奇岩などの日常風景から外れるものばかりと。そして志賀の本質は国粋主義者ではなく、英米崇拝者だと結論づけている。何故ならかなり無理をして西洋的で壮大な風景を拾い出そうとしたと。(産経新聞,2018.6.4,「明治の50冊」)
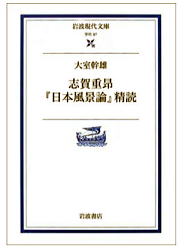
最後に是非つけ加えねばならないことは、当時の識者の代表とも言うべき、内村鑑三の指摘である。志賀の「日本風景論」の中に、書評子をも含めた読者に誘いこむ「ワナ」が大っぴらに仕掛けてあったと言うのである。
それを指摘して、内村鑑三は「Patriotic Bias(愛国偏)」と呼んだという。そしてその内村も、帝国最初の対外戦争を熱烈に支持していたと言うのだから、もう何をか言わんやである。この様な文脈からすれば、「大日本的精神」は、日本の風景と相関関係にあり、その精神によって連戦連勝しているときに、「日本風景の万国に卓絶する所以」を説いた志賀の「大著」の出現は必然だったのだと結論づけることが出来るだろう。 ―END−