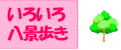 |
5月10日(土) 角 紘康(参加者) |
●住を構え、後に平将門伝説の地であることを知るが、それを多少頭の隅に残しながら我孫子の地を10数年間離れたが帰り、定年退職し、今回の機会を得て参加させていただいた。
●湖北台と湖北中央公園は、緑が多く、整備された美しい空間は西洋的な雰囲気を醸し出す。中里諏訪神社は、古木が有り、中里薬師堂は昔より住人が守ってきた由緒ある祠。中里市民の森(下の写真)とかまくら道は、緑の多い地で、当時の「いざ鎌倉」と馳せ参じる騎馬武者を想像するのも楽しいものである。手賀沼殉難教育者の碑は、戦時中手賀沼で助教員錬成会参加者が突風を受け、尊い命を落とした状況を、暗い碑に当時を伺えるような気がする。
 |
| 中里市民の森 |
●最後に訪れた「中里通りのまちなみ」の星野家長屋門(下の写真)中野家の四つ足門は、一気に昔にタイムスリップした感じを受ける。我孫子市は比較的新しい町という感から、歴史諸説が絡む不思議な町である。
 |
| 星野家 長屋門 |
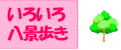 |
5月24日(土) 宮田 弘(会員) |
●あやめ通りを進み小暮橋(下の写真)に到着。小さな橋ながら周囲の自然と調和し、どこか懐かしさを感じさせます。春には桜が咲き誇り、地元の写真愛好家たちの隠れた撮影スポットでもあります。
| 小暮橋・・・下を成田線が通る |
●日立坂を下り、高野山へと向かいます。高野山桃山公園の麓に広がるビオトープは、大きくはないものの、よく整備されていて、自然がそのまま息づいています。この麓の水は、台地に降った雨水が20年かけて濾過され、湧き出てきた水だそうです。
| 水神山古墳で説明を聞く |
●続いて訪れたのは前原古墳。市内最古の古墳とされています。ここからは手賀沼の絶景が一望できました。この一帯には、古墳が点在していたという記録があり、我孫子が古くから文化の交差点であったことを示しています。近くには生活の音がありながら、地面の下には太古の眠りが広がっている。その対比がとても印象的でした。
●最後に訪れたのが、地元の人々に愛されている高野山桃山公園。広場や遊具、散策道が整備された公園です。
●大きな観光地のような派手さはないけれど、我孫子の古墳と公園には、時代を超えた静かな魅力がありました。日々の忙しさの中で忘れかけていた足元の歴史に気付かさせてくれる、そんな優しい時間でした。