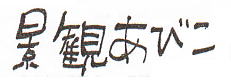
発行人 吉澤淳一
我孫子市つくし野6-3-7
編集人 飯田俊二
| 我孫子の景観を育てる会 | 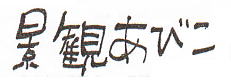 |
第45号 2011.9.17発行 発行人 吉澤淳一 我孫子市つくし野6-3-7 編集人 飯田俊二 |
| ●北小金に50年以上住み、我孫子にはリタイア前の2年半勤務しただけで、今までこのシリーズを書かれた方々のような生活者の視点は持っていませんが、私なりの我孫子への想いを書いてみます。 ●私は10歳まで茨城県佐貫に住んでいて、常磐線で我孫子を通るときは、決まって駅近くの緑濃い環境のなか白い建物の「日立精機」を眺め、きれいな工場だなあと強い印象を持っていました。また佐貫は牛久沼が近くにあり、牛久沼の夕方の風景もかすかに覚えています。手賀沼への親しみの底流がこのへんにあるのでしょう。その後、北小金に住み現在に至っています。この頃家にセパードがいましたが、父が「この犬は我孫子のお寿司屋さんからもらってきた」と言っていたのを鮮明に覚えています。両親とも実家が成田方面であったので、成田線の時間待ち等のため我孫子のお店を使っていたものと思います。当時の我孫子駅には藤代よりに蒸気機関車の向きを変える「転車台」があったのも覚えています。この二つが自分のなかの我孫子の原風景です。 ●我孫子への通勤初日の朝、改札を出ようとして驚いたのは、改札へ入ってくる人が圧倒的に北口からのほうが多かったことです。私のイメージの我孫子は手賀沼や旧市街のある南口のほうでした。勤務場所は大光寺の近くで、朝夕の通勤時に駅の改札近くの掲示板でいろいろの催しを知り、休みの日に旧本陣の村川別荘や、あやめ祭りに出かけました。だんだん慣れるにしたがい、楚人冠公園、天神坂、三樹荘、志賀邸跡など曲がりくねった昔の道を勤務後に散策するようになりました。 ●かつて我孫子は文人等の別荘地として有名で、「北の鎌倉」と言われたときもありました。私が住む北小金も「北の鎌倉」と言われたこともあったようですが、これは日蓮宗本山「本土寺」(あじさい寺)と浄土宗十八壇林のひとつ「東漸寺」という格の高いお寺があり、そのほかにも多くの寺があることからです。 ●北小金には水戸街道の宿場小金宿があり、次の宿場が我孫子宿です。小金宿は本陣・脇本陣があった我孫子宿とちがい小規模な宿場ですが、南のはずれに江戸時代の旅籠が一軒当時の姿を伝えています。近年は町おこしとして「小金宿まつり」が開催され、街灯にも「小金宿」のプレートが付けられています。 |
●我孫子宿の脇本陣は残っているようですが、茅葺きの屋根しか見えません。江戸時代から続く宿屋の「角松本店」の前を通勤時朝夕通っていました。和のいい雰囲気ですが、気軽に利用できそうではなく、中も知りませんでした。千葉から通っていた所長が台風時の運休に備えてここに宿泊し、よかったというのを聞いて、ホームページを調べてみました。宿の歴史として明治天皇が茨城県女化原(女化=おなばけと読み、私が住んでいた佐貫の近くで女化神社があり、子供ごころに何と変わった地名だろうと感じていました)で行われた近衛師団演習統監の行在所になったとの記述がありました。前泊の小金にもかつて郵便局があったところに明治天皇行在所の石碑があります。 ●我孫子の昔の町並みは南に手賀沼という湖水をおいた高台にあり、住むには最上の条件を備えています。 ●手賀沼あってこその我孫子であり、存在の大きさについては今まで皆さんがいろいろ書いてこられて、改めて書くほどのことはありませんが、七月のあるとき、6号線をオートバイで下ってきて、北柏からふれあい道路に入るあたりで一陣の涼しい風を浴びたときは手賀沼という広い水面のありがたさを身にしみて感じたことでした。 ●旧水戸街道、356号は駅前から東我孫子に向けて2箇所急カーブがあり昔の街道のおもかげを残しています。最初のカーブには角松本店があります。門のところに見事な松があり、その手入れの様子は大変興味深いものでしたが、数年前枯れて切られてしまいました。この区間は先年拡幅の改良工事が行われましたが、街路樹が植えられなかったのは残念です。2番目のカーブにある元旅館の鈴木屋本店は玄関部分が古いつくりで趣があり、三叉路の角にあるので目立ちます。市内の356号の大半は現代風の箱状の建物ばかりなので、この二つの和風の雰囲気ある建物は印象が強いものがあります。このごろ流行の鉄道模型のジオラマ(情景作り)では圧倒的に木造駅舎、木造建物の昭和レトロ風が人気です。景観散歩で行った、佐原、土浦、古河、真壁など何れも古い建築物を大事にしています。 ●今秋には楚人冠邸が復元・公開されますが、作家・画家の広い邸宅はどこも有力な観光スポットであり、建物好きとして大変期待しているところです。 |
| ■もどる | ■「私の我孫子らしさ」シリーズの目次へ |