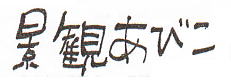
編集・発行人 吉澤淳一
我孫子市つくし野6-3-7
| 我孫子の景観を育てる会 | 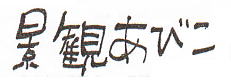 |
第56号 2013.7.20発行 編集・発行人 吉澤淳一 我孫子市つくし野6-3-7 |
大光寺参道の公孫樹(イチョウ)が3本消えたが? オオバン通り、新道路の緑化に貢献か |
|||||||
| ●都市計画道路3・4・14号「手賀沼公園・久寺家線道路整備」と356号道路の交差点にあたる大光寺参道に並ぶ「イチョウ」が伐られていると会員の飯田さんからの報せに、兎にも角にもそそくさと、見に出かけた。 ●移植か?伐られるのか?・・・行政の遂行計画と市民の惜しまれる気持ちの狭間にあったイチョウの運命に、処分の時期まさに到来!であった。 入り口から3本が、いともカンタンに伐られて車に積み込まれていた。 ●平成20年8月22日市の交通課から、3・4・14号計画道路の現地説明を受け、356号入り口のイチョウの5本のうちの3本と欅が邪魔になると言われ、当時「景観あびこ」の編集責任者であった清水昭子さんが、「此のイチョウの大木は街の緑確保の為に、日比谷公園の「首かけのイチョウの故事に倣って移植してでも保存して欲しい」と心情を語っておられた記憶が今も生々しい。
|
●一抱えも二抱えもある長寿大木は「人に感動をあたえる」、先日訪問した大光寺のご住職が「明治生れの先代が植樹したもので、地名のー緑ーに相応しい樹であった」とひかり幼稚園に聳えるイチョウを見上げながら、しみじみ語っておられたが、我孫子らしい緑豊かな風景に育まれた人々には、永遠に残って欲しいものだったでしょう。 ●しかし、移植には移植先と費用の問題があった。持ち主の大光寺さんの決断もあったのでしょうが、都市マスタープラン、文化拠点整備計画、緑の基本計画など市の抱える高度の計画を推進することは人口減少・平均年齢の高齢化移行を目の辺りにして、我孫子市観光の目抜き通りとなる「公園坂通りの改修」に一日も早く着手して貰う事が必要です。 ●期待を再三引き伸ばされた、「3・4・14号計画道路」が"平成27年3月に完成されることを大前程"にすれば、この3本のイチョウこそ「我孫子将来の為の礎石としての想いに値するもの」として皆さんの心に留め置き願いたい思いです。(左の写真は伐採後の景色)
|
||||||
| ■もどる | ■「私の我孫子らしさ」シリーズの目次へ | ||||||